1. 予算とは何か
予算とは、ある期間に使うお金の「計画」を数字で表したものです。
個人でも企業でも、自治体や国でも、活動を行うためにはお金の管理が必要です。
そのとき、ただ支出するのではなく「いつ・どこに・いくら使うか」を事前に決めることで、無駄をなくし、計画的な運営ができます。
この計画のことを「予算」と呼びます。
たとえば、家庭でも「今月は食費にいくら、光熱費にいくら」と決めて生活することがあります。
同じように、役所や企業も「年度のはじめ」にお金の使い方をあらかじめ決めておきます。

2. 予算の役割
予算には主に3つの役割があります。
- 計画の指針になる
- お金の使いすぎを防ぐ
- 責任と説明の根拠になる
例えば、市役所で道路整備をする場合、事前に予算を計上していなければ工事に着手することはできません。
逆に、計画より多く使ってしまうと、財政が赤字になったり、説明責任が発生します。
つまり、予算は単なる「数字」ではなく、組織を動かすためのルールの一部です。

3. 予算と決算の関係
予算が「計画」なら、決算は「結果」です。
1年間など一定期間が終わったあと、実際に使ったお金と予算を照らし合わせて「きちんと使えたか」を確認します。
この予算と決算の関係を理解することは、財務の基本です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予算 | あらかじめ決めたお金の使い方 |
| 決算 | 実際に使ったお金の結果 |
| 差額 | 余った/足りなかった金額 |
もし予定よりも支出が少なければ「不用額」として処理され、逆に多ければ補正が必要になる場合もあります。
4. 予算の種類
予算にはいくつかの分類があります。
初心者がまず押さえておきたいのは「一般会計」と「特別会計」の違いです。
- 一般会計:通常の業務全般の経費(例:人件費、施設の維持費)
- 特別会計:特定の事業のために分けられた予算(例:国民健康保険、水道事業など)
このように、お金の使い道や目的によって「会計」を分けることで、管理がしやすくなります。
また、予算は「歳入(入ってくるお金)」と「歳出(出ていくお金)」で構成されます。
5. 歳入と歳出の基本
予算は収入と支出のバランスで成り立っています。
これを行政では「歳入(さいにゅう)」と「歳出(さいしゅつ)」と呼びます。
歳入(収入)
行政でいう歳入には次のようなものがあります。
- 税金(住民税、固定資産税など)
- 国や県からの交付金・補助金
- 使用料や手数料
- 繰入金や借入金
歳出(支出)
一方の歳出には次のようなものがあります。
- 職員の人件費
- 道路・施設の整備費
- 福祉や教育への支出
- 債務(借金の返済)
この歳入と歳出をバランスよく組み立てることで、予算が成立します。
6. 行政の予算編成の流れ
行政機関では、毎年「予算編成」という大きな作業があります。
これは、次年度に向けてお金の使い道を決めるプロセスです。
大まかな流れは以下のとおりです。
- 各課から予算要求を提出
- 財政課などが内容を精査
- 首長(市長・知事など)が予算案をまとめる
- 議会に提出して審議
- 議会の議決を得て成立
特に、各課の担当者が行う「予算要求」が重要です。
ここで適切な金額を見積もらなければ、必要な事業が進められなくなる可能性もあります。
7. 予算要求のポイント(実務イメージ)
実務では、予算要求書に「必要な理由」「金額」「事業の効果」などを記載して提出します。
例えば、窓口の混雑緩和のために新しいシステムを導入したい場合、以下のような内容になります。
- 目的:窓口業務の効率化
- 内容:システム導入と端末購入
- 金額:500万円
- 効果:待ち時間短縮、職員の負担軽減
財政担当はこの要求を精査し、優先順位をつけながら予算案に組み込みます。
この段階での説明力が、事業実現の鍵となります。
8. 補正予算と本予算の違い
予算には「本予算」と「補正予算」があります。
- 本予算:年度当初に編成される基本の予算
- 補正予算:年度途中に追加や変更を行うための予算
たとえば、大規模な災害が発生して新たな支出が必要になった場合、補正予算を組むことで対応します。
予算は一度決めたら終わりではなく、状況に応じて柔軟に見直すことも可能です。
9. 執行と予算管理
予算が成立したら、それを実際に「執行(しっこう)」していきます。
執行とは、予算に基づいて実際にお金を使うことです。
たとえば、予算で計上していた備品購入費を使ってパソコンを購入する、といったことがこれにあたります。
執行の際には次のような管理が重要です。
- 執行残高の確認(使える金額が残っているか)
- 支出の根拠書類の整備
- 予算超過の防止
- 支出の時期の調整
予算管理がしっかりしていないと、年度末に「使いすぎ」や「使い残し」が発生し、次年度の予算に悪影響を与える可能性もあります。
10. 予算と説明責任
予算は公共のお金です。
特に行政では、市民や国民からの税金で成り立っているため、使い方には説明責任が伴います。
- なぜその事業が必要なのか
- なぜその金額が必要なのか
- どのような効果があるのか
これらをきちんと説明できなければ、議会や住民からの理解は得られません。
「お金の流れを透明にすること」が信頼の基本です。

11. 具体例:市役所の予算の流れ
たとえば、市役所で新しい庁舎を建てる場合の予算の流れを簡単に見てみましょう。
- 建設課が必要な金額と内容を予算要求
- 財政課が他事業とのバランスを見て調整
- 予算案として議会に提出
- 議会で審議・承認
- 実際の設計・施工が始まる
- 工事費を支払い、決算で精算
このように、1つの事業でも予算が関わる範囲は広く、関係部署も多くなります。
だからこそ、正確な見積もりと管理が欠かせません。
12. 初心者が押さえるべきポイント
予算の世界は専門用語も多く、最初は難しく感じるかもしれません。
しかし、基本を押さえると全体像が見えやすくなります。
- 予算は「お金の計画」である
- 歳入(収入)と歳出(支出)のバランスが重要
- 年度当初の本予算と、必要に応じた補正予算がある
- 予算要求→議会審議→執行→決算という流れを理解する
- お金を使うには「説明責任」が伴う
これだけでも、予算関連の会議や書類の内容がぐっと理解しやすくなります。
13. まとめ
予算の仕組みは、行政でも企業でも基本となる知識です。
特に自治体や公務員の世界では、予算はすべての事業の出発点になります。
- 予算=お金の使い方を決める「計画」
- 予算→執行→決算の流れを理解する
- 補正予算で柔軟に対応する仕組みがある
- 透明性と説明責任が非常に重要
予算の仕組みを理解することは、業務の正確性と信頼性を高めるうえで欠かせません。
初心者のうちに基本をしっかり身につけておくことで、今後の実務にも大きく役立ちます。


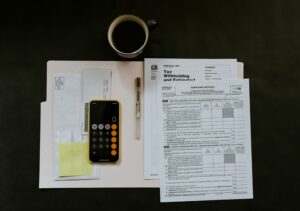





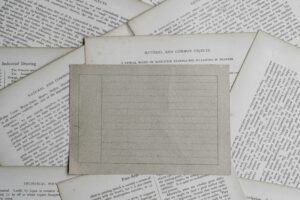

コメント