1. 料金後納とは何か
「料金後納(りょうきんごのう)」とは、郵便物を発送する際に、その場で切手や現金を支払わず、あとでまとめて料金を支払う方法のことです。
たとえば、企業や自治体などが大量の郵便物を発送する場合、1通ずつ切手を貼って窓口に持ち込むのは手間がかかります。
そこで便利なのがこの「料金後納制度」です。
料金後納を使えば、発送時の支払い作業を省略し1か月分などをまとめて支払うことができます。
役所や企業などの事務では、非常によく利用される制度です。

2. 料金後納と通常の発送との違い
通常の郵便物は、発送のたびに料金を支払います。切手を貼ったり、窓口で現金を支払ったりする方法です。
一方、料金後納は「発送時には支払いをせず、あとで一括精算」します。
| 項目 | 通常の郵便 | 料金後納 |
|---|---|---|
| 支払い方法 | 1通ごとに切手や現金 | 後日まとめて支払い |
| 対象 | 個人・法人 | 法人・自治体など(一定条件あり) |
| 手間 | 毎回支払いが必要 | 発送時の支払い不要 |
| 利用条件 | 特になし | 契約・事前申請が必要 |
特に、毎月大量に郵送物を出す部署では、料金後納を使うことで事務の負担を大きく減らすことができます。
3. 料金後納の基本的な仕組み
料金後納を利用するためには、あらかじめ郵便局と契約をしておく必要があります。
申請・審査を経て「料金後納郵便」の利用が認められると、次のような流れで発送ができます。
- 郵便局と契約・登録
- 専用の差出票や料金後納表示を準備
- 郵便物をまとめて郵便局に差し出し
- 郵便局が1か月分を集計
- 後日請求・支払い
つまり、事前に契約を結んでおけば、発送時に窓口で細かいやり取りをせずに郵便物を出せる仕組みです。
4. 料金後納の対象となる郵便物
料金後納で送ることができるのは、特定の種類の郵便物です。
主な対象は次のとおりです。
- 普通郵便(定型・定形外)
- ゆうメール
- 料金別納の対象となる郵便物
- 一部の特殊取扱郵便(書留など)
ただし、速達や簡易書留など特殊なサービスを使う場合は、事前の契約内容によって取り扱えるかが異なります。
また、1回の差し出し部数が一定数(通常は10通以上)必要です。
5. 料金後納のメリット
料金後納を利用する大きなメリットは、事務の効率化と支払い処理の簡素化です。
(1)切手を貼る手間が不要
1通ずつ切手を貼る必要がなくなります。大量発送のときに特に効果が大きく、作業時間を大幅に削減できます。
(2)毎回の支払いが不要
発送時に窓口で現金やカードを出す必要がありません。月に1回などまとめて精算できるため、経理処理もシンプルになります。
(3)料金の一括管理が可能
発送量や料金が一覧化されるため、予算管理や発送実績の把握が容易です。
経理や財務と連携した処理もしやすくなります。
6. 料金後納のデメリット・注意点
一方で、料金後納には注意すべき点もあります。
(1)契約が必要
個人では基本的に利用できません。事前に郵便局との契約が必要で、申請書類の提出や審査があります。
(2)利用条件がある
・差し出し通数の下限(10通以上)
・専用表示の印刷(料金後納マーク)
・差出票の記入など、一定のルールを守る必要があります。
(3)支払い管理が必要
後で一括請求されるため、支払時期をきちんと管理しておかないと、支払い忘れや遅延が発生するリスクがあります。
(4)発送数が少ない場合は不向き
1日に数通しか出さない場合は、逆に管理の手間が増えることもあります。
料金後納は「大量発送向け」の制度です。
7. 料金後納の表示(料金後納マーク)
料金後納を利用するには、郵便物に**料金後納表示(マーク)**を印刷する必要があります。
これは切手の代わりになるもので、料金の支払い方法が後納であることを示すものです。
通常、封筒の右上に「料金後納郵便」と印刷します。
また、表示には契約者の住所・名称などを記載する必要があります。
この表示がなければ、料金後納郵便として受け付けてもらえません。
8. 料金後納の申請・契約方法
料金後納を利用するためには、郵便局で以下の手続きが必要です。
- 利用を希望する郵便局に申請
- 契約書・申込書の提出
- 審査・登録
- 契約番号の発行
- 封筒やはがきに料金後納表示を印刷
審査にはある程度の発送実績や信用情報が必要になる場合もあります。
自治体や企業ではよく使われますが、個人事業主では事前の相談が必要です。

9. 差出票と発送管理
料金後納郵便を出すときは、郵便物と一緒に「差出票」を提出します。
差出票には次のような項目を記入します。
- 日付
- 部数(何通発送するか)
- 種類(定型、定形外、ゆうメールなど)
- 金額
- 担当者名
郵便局はこの差出票をもとに1か月分の料金を集計し、後日請求します。
そのため、差出票の管理や控えの保管は非常に重要です。
10. 実務でありがちな注意点
料金後納の事務では、次のような点でミスが起きやすいので注意が必要です。
(1)差出票の記載漏れ
発送部数の数え間違いや記入漏れがあると、請求金額がずれてしまうことがあります。
(2)表示マークの不備
料金後納マークが正しく印刷されていないと、差し戻しになるケースもあります。
(3)発送部数の集計ミス
月末に発送部数と郵便局の請求が一致しないケースは実務でもよくあります。
差出票と発送記録をしっかり残すことで防げます。
(4)少数の発送時の対応
10通未満で差し出したい場合は、後納ではなく通常の切手や料金別納に切り替える必要があります。
11. 料金別納との違い
よく混同されやすいのが「料金別納」との違いです。
- 料金別納:発送時にまとめて支払い
- 料金後納:発送後にまとめて支払い
| 項目 | 料金別納 | 料金後納 |
|---|---|---|
| 支払いタイミング | 差し出し時 | 後日一括 |
| 契約 | 不要(届出のみ) | 契約が必要 |
| 少数発送 | 可 | 不可(10通以上) |
| 利用者 | 個人・法人 | 主に法人・自治体 |
事務でどちらを使うかは発送量や事務フローによって決めると効率的です。
12. 支払いと経理処理
料金後納の請求は、1か月分をまとめて郵便局から送られてきます。
自治体などでは、財務担当課で支払い処理を行い、発送部門は差出票を提出します。
経理処理上では次のような流れが一般的です。
- 月末または翌月初に請求書受領
- 発送実績と請求書の突合
- 支払い伝票の起票
- 支払い処理(口座振替や現金支払い)
発送実績と請求額が一致しているかの確認が特に重要です。
ここでミスがあると、年度末の決算処理にも影響が出る可能性があります。

13. 料金後納の活用例
実際の活用例を紹介します。
例1:自治体の通知発送
市役所で住民へのお知らせ文書を一斉に送るとき、料金後納を利用。
1回の発送が1万通を超える場合でも、切手を貼らずに窓口提出が可能。
例2:企業の請求書発送
企業が毎月取引先に請求書を郵送する場合にも料金後納を活用。
毎回の発送処理が効率化され、経理処理も月1回に集約できる。
14. 料金後納を使うときのポイントまとめ
- 契約が必要(個人利用は基本不可)
- 差し出し通数は10通以上
- 専用の料金後納表示が必要
- 差出票の記録と管理が重要
- 経理処理との連携を意識する
料金後納は便利な制度ですが、ルールを守らないと受け付けてもらえなかったり、請求額のズレが生じたりするため、事務担当者の管理力が問われる業務です。
15. まとめ
料金後納は、大量の郵便物を効率よく発送するための便利な仕組みです。
- 発送時の支払いが不要で、事務の効率が大幅に向上する
- 契約とルールを守る必要がある
- 差出票や表示マークなど、実務的な注意点が多い
- 料金別納との違いを理解しておくと混乱が少ない
特に自治体や企業の事務担当にとって、料金後納を正しく理解しておくことは、日常業務の効率化につながります。
ミスが起きやすいポイントを押さえ、記録と管理を丁寧に行うことがスムーズな運用のカギです。


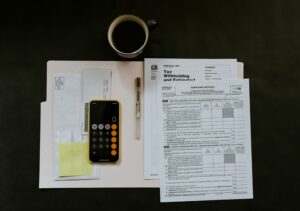





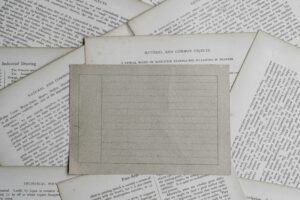

コメント